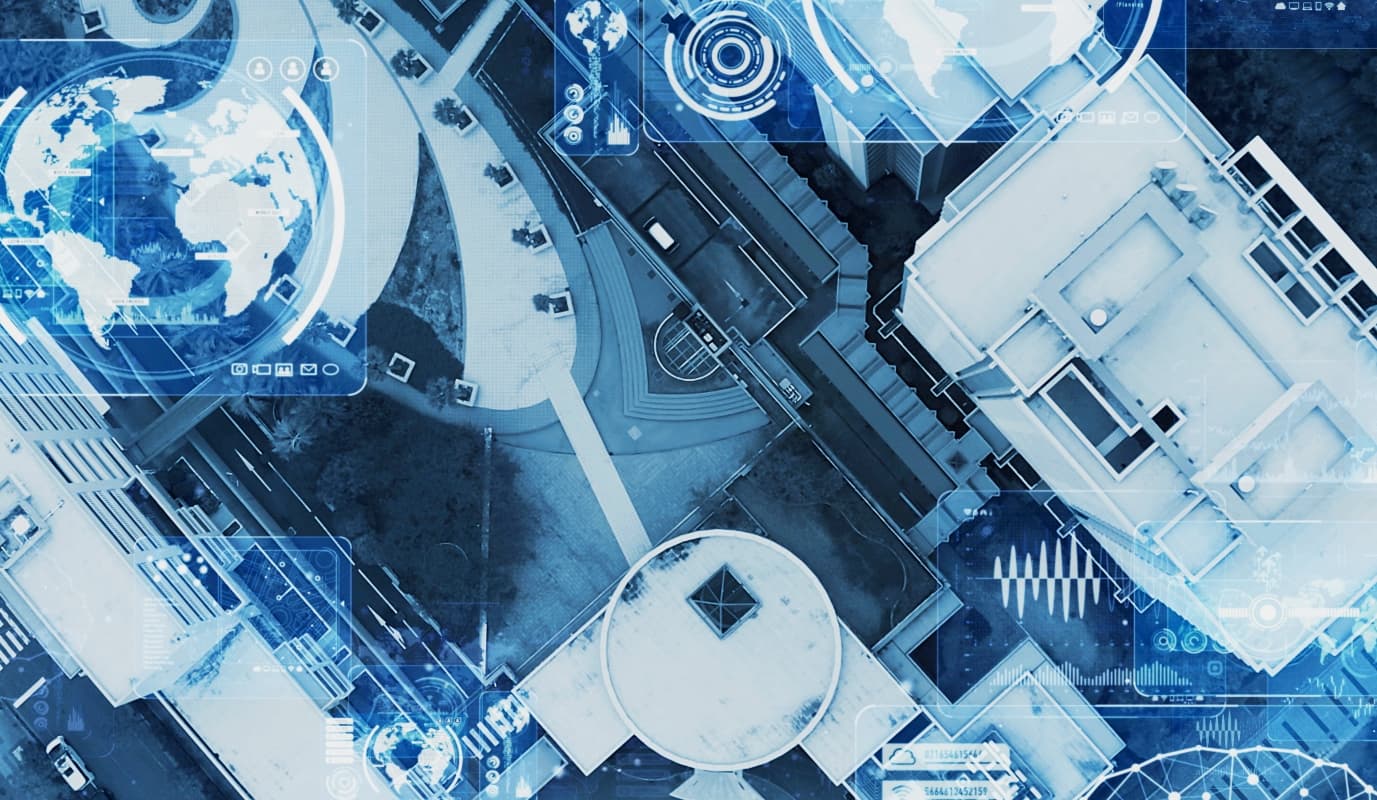PROJECT STORY
ドコモのプロジェクト事例

13
スマート農業
農業経営を可視化し、
見えない営農データ収集を実現
見えない営農データ収集を実現
OUTLINE
2019年、農林水産省がスマート農業の実証実験を開始しました。全国69地区の農地を対象に、ロボットやAI、IoT(※)などを活用した実験的な施策を投下。ドコモビジネスが参加したのは、そのうちのひとつである「スマート農業技術導入による地域水田農業の活性化プロジェクト」。
農産物の生産コストの可視化に取り組み、データに基づく農業経営をしていくための “物差し”を作ることに成功しました。これによりスマート農業などの導入による生産コストへの影響の把握が可能となり、最先端テクノロジーがどのようなインパクトを与えるのかを証明できるようになりました。
農業をスマート化した際の成果を客観的に把握できるようになることで、今後の研究を一気に飛躍させる可能性が開けてきたのです。プロジェクトメンバーが当時を振り返ります。
※ IoT(アイ・オー・ティー)…「Internet of Things」の略。モノがインターネット経由で通信することを指す。
農産物の生産コストの可視化に取り組み、データに基づく農業経営をしていくための “物差し”を作ることに成功しました。これによりスマート農業などの導入による生産コストへの影響の把握が可能となり、最先端テクノロジーがどのようなインパクトを与えるのかを証明できるようになりました。
農業をスマート化した際の成果を客観的に把握できるようになることで、今後の研究を一気に飛躍させる可能性が開けてきたのです。プロジェクトメンバーが当時を振り返ります。
※ IoT(アイ・オー・ティー)…「Internet of Things」の略。モノがインターネット経由で通信することを指す。
PROJECT MEMBER
私たちが紹介します

プラットフォームサービス本部
データプラットフォームサービス部
データプラットフォームサービス部
Suzuki Yoichi
鈴木 与一
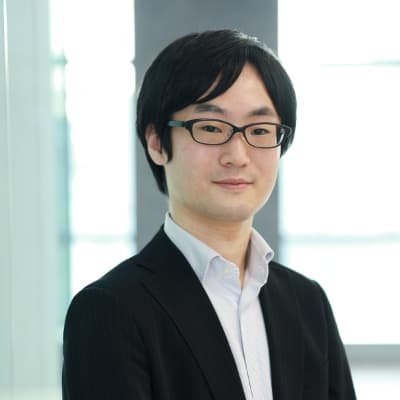
プラットフォームサービス本部
データプラットフォームサービス部
データプラットフォームサービス部
Suzuki Masataka
鈴木 理昂

ビジネスソリューション本部
ソリューションサービス部 ICTイノベーション部門
ソリューションサービス部 ICTイノベーション部門
Inoue Keisuke
井上 圭介

ビジネスソリューション本部
ソリューションサービス部 ICTイノベーション部門
ソリューションサービス部 ICTイノベーション部門
Sahara Ryouma
佐原 良馬
ROAD MAP
-
Phase 01 事業参画
スマート農業の実証実験に挑む、「岩見沢スマート農業コンソーシアム」から、農産物の生産コストを可視化するためのデータの収集手段としてドコモビジネスのIoTプラットフォーム『Things Cloud®』が採用された。
-
Phase 02 設計
『Things Cloud®』によって収集した農作業に関するデータをいかにコンソーシアムの分析基盤に連携するか。
-
Phase 03 構築
営農データを収集するための各デバイスから発信されるデータから農作業の生産性に関するデータを取得。
-
Phase 04 実証実験
スマート農業の実証実験を開催。『Things Cloud®』とデバイスにより、農産物の生産コストを可視化するためのデータを収集・送信。
-
Phase 05 成果発表
農産物の生産コストの可視化に成功。スマート農業の実践により、農作業の生産性が向上することが証明された。
Phase 01
事業参画
農産物の生産コストを可視化するために
きっかけは、設計のリーダーを務めた鈴木与一の知人でした。岩見沢スマート農業コンソーシアムが農林水産省のプロジェクトに参加することになり、その一画を担う農業系スタートアップ企業から声がかかったのです。「われわれが手掛けるIoTプラットフォーム『Things
Cloud®』の資料を見て、ぜひ力を貸してほしいとのことでした」と当時を振り返る鈴木与一。同コンソーシアムは農業活性化におけるさまざまな施策を計画しており、その中のひとつに「データに基づく農業経営の実現に向けた農産物の生産コストの可視化」というテーマがありました。現在、農家が一般的に利用しているアナログの農機では作業情報を取得することができず、生産コストの把握には大きな作業負担がかかる状況でした。既存農業の生産コストを可視化できなければ、スマート農業の成果を可視化することもできません。さらに、各メーカーがそれぞれ独自の仕様でデータを送信しているため、農作業に関わる多種多様なデータを一元管理することも容易ではありませんでした。しかし、Things
Cloud®ならそれができます。
「このプロダクトの特徴は、あらゆるメーカーの農機と接続できること。その強みを発揮すれば、ありとあらゆる農作業のデータを蓄積することができます」。実証実験後、スマート農業を広く普及させることまで見据えれば、デバイスや農機を選ばず接続できるThings Cloud®の存在意義は決して軽くはありませんでした。
「このプロダクトの特徴は、あらゆるメーカーの農機と接続できること。その強みを発揮すれば、ありとあらゆる農作業のデータを蓄積することができます」。実証実験後、スマート農業を広く普及させることまで見据えれば、デバイスや農機を選ばず接続できるThings Cloud®の存在意義は決して軽くはありませんでした。

Phase 02
設計
Things Cloud®初の外部システムとの連携
今回、岩見沢スマート農業コンソーシアムが挑んだ実証実験に関わるデータはすべて「生産原価データ活用サービス」というシステムに集約され、さらに農業データ基盤を通じて分析結果が表示される仕組みになっていました。ドコモビジネスが担当したのは、そのうちの「作業記録および、農作業者・農作業機の位置情報」の取得。必然的にThings
Cloud®は外部システムにデータを送信することになります。しかし、これが大きな壁となったのです。
「Things Cloud®を利用すれば、さまざまな位置情報を一元管理することはできます。しかし、そのデータをさらに外部に送るというのは初の試みだったのです」と語るのは、設計を担当した鈴木理昂です。「データの転送自体は難しいことではありません。しかし、これは実証実験の成果を左右する極めて重要な情報です。データの重複を回避しながら、リアルタイムかつ安定的に位置情報を届けなければなりませんでした」。
コストとスピードの問題もあります。実証実験である以上、湯水のように予算を使うわけにはいきません。しかも、納期までの時間はわずか2ヵ月ほど。「なんとか農業が盛んになる季節までに間に合わせる必要がありました。あらゆるリスクを検討した結果、最終的に5分毎に情報を送るという結論に着地。システムをつくるのではなく、Things Cloud®の機能をカスタマイズすることで、コストとスピード、そしてリアルタイム性を両立させたのです」。
「Things Cloud®を利用すれば、さまざまな位置情報を一元管理することはできます。しかし、そのデータをさらに外部に送るというのは初の試みだったのです」と語るのは、設計を担当した鈴木理昂です。「データの転送自体は難しいことではありません。しかし、これは実証実験の成果を左右する極めて重要な情報です。データの重複を回避しながら、リアルタイムかつ安定的に位置情報を届けなければなりませんでした」。
コストとスピードの問題もあります。実証実験である以上、湯水のように予算を使うわけにはいきません。しかも、納期までの時間はわずか2ヵ月ほど。「なんとか農業が盛んになる季節までに間に合わせる必要がありました。あらゆるリスクを検討した結果、最終的に5分毎に情報を送るという結論に着地。システムをつくるのではなく、Things Cloud®の機能をカスタマイズすることで、コストとスピード、そしてリアルタイム性を両立させたのです」。

Phase 03
構築
位置情報の送信を安定化
実証実験に向け、プロジェクトチームはトラクターに取り付ける車載器と農作業者に持たせるスマートフォンを調達しました。これらのデバイスが発信する位置情報をもとに、畑に入った瞬間を作業時間、それ以外を非作業時間として生産コストを算出する際の足掛かりにしようとしました。「しかし、ここで大きな問題があることに気づいたのです」と語るのは、構築のリーダーを務めた井上圭介です。スマートフォンには省エネルギーやセキュリティの観点から、バックグラウンドで起動しているアプリを一定時間で自動停止する機能が備わっています。これでは長時間におよぶ農作業の位置情報を取得することはできません。
「スマートフォンと一言で言っても、各メーカーがさまざまな仕様で開発しています。今後の普及のことも視野に入れると、この問題は絶対に解決しなければならないハードルのひとつでした」。
端末を変えるという選択肢もあったが、井上たちは試行錯誤を繰り返し、端末が不要な送信だと認識しない方法を模索。丸一日動かしても正確にデータが取得できる“解”を見つけることに成功したのです。
「スマートフォンと一言で言っても、各メーカーがさまざまな仕様で開発しています。今後の普及のことも視野に入れると、この問題は絶対に解決しなければならないハードルのひとつでした」。
端末を変えるという選択肢もあったが、井上たちは試行錯誤を繰り返し、端末が不要な送信だと認識しない方法を模索。丸一日動かしても正確にデータが取得できる“解”を見つけることに成功したのです。

Phase 04
実証実験
不確実な現場でデータ取得に成功
2019年の6月、プロジェクトチームは北海道岩見沢市へ飛びました。この地の4つの農家の畑が、実証実験の舞台となります。「当日、農作業者の方々にスマートフォンアプリの使い方を説明しました。なかにはICTに慣れていない方もいらっしゃるので、操作は極めてシンプルなものにしています」と語るのは構築を担当した佐原良馬です。農作業者たちは出勤前にアプリをタップするだけで、実験に必要な情報が送信されます。今回の実験だけでなく、全国で利用されたときのことも想定し、説明書も大きな写真、大きな文字で3ページほどに簡潔にまとめました。「あとは実験を開始するのみでした。ただ、現場での運用は初めてだったので多少の不安があったことも事実です」。
実証実験は、見渡す限り畑という広大な敷地のなかで行われます。端から端までは、車で1時間ほど。電波が安定しているかどうかは直接、自分たちの目で確かめるしかありませんでした。「当日は歩き回りながらチェックするメンバーと、Things Cloud®にデータが送信されているかどうかをチェックするメンバーに分かれました」。幸い、佐原たちの心配は杞憂に終わりました。すべてが安定的に稼働し、Things Cloud®には位置情報がどんどん飛び込んできたのです。農作業中に端末が故障することも危惧していましたが、念のために用意していた予備機が登場する機会はなかったと言います。「予備日を使うこともなく、実証実験は無事に終了。この瞬間はさすがにホッとしました」。
実証実験は、見渡す限り畑という広大な敷地のなかで行われます。端から端までは、車で1時間ほど。電波が安定しているかどうかは直接、自分たちの目で確かめるしかありませんでした。「当日は歩き回りながらチェックするメンバーと、Things Cloud®にデータが送信されているかどうかをチェックするメンバーに分かれました」。幸い、佐原たちの心配は杞憂に終わりました。すべてが安定的に稼働し、Things Cloud®には位置情報がどんどん飛び込んできたのです。農作業中に端末が故障することも危惧していましたが、念のために用意していた予備機が登場する機会はなかったと言います。「予備日を使うこともなく、実証実験は無事に終了。この瞬間はさすがにホッとしました」。

Phase 05
成果発表
舞台裏から日本の自給率向上を支える
実証実験は、農作業が難しくなる冬が訪れるまで続きました。その後、春を待って再開。プロジェクトチームが取得した位置情報は「生産原価データ活用サービス」に送られ、農業データ基盤を通してさまざまな生産コストが可視化されました。収集・分析されたデータを見れば、岩見沢スマート農業コンソーシアムによる今回の実証実験は、スマート農業施策がもたらすインパクトの大きさを証明することとなりました。その裏にはThings
Cloud® を活用し、データに基づく農業経営のための、農産物生産コストという“物差し”を作りあげたプロジェクトチームの存在があります。
「生産者の方々の喜びの声はもちろんですが、コンソーシアムに参加し、スマート農業を推進する立場にある事業会社の方たちから感謝されたことも大きかった」と語る鈴木与一。メーカーの枠を越えてさまざまなデータを一元管理できるThings Cloud®の名前を覚えた事業会社も多かったに違いありません。
「ドコモビジネスとしては、今回のような農業の実証実験に参加するのは初めてのことでした。この機会を通じて農業はもちろん、水産業といった日本の自給率を支えるプロジェクトに携わっていけたらと考えています」と笑顔を見せる鈴木与一だが、自分たちはあくまでも舞台裏から支えるのが仕事だと言います。
「今回のプロジェクトの主役は、コンソーシアムの方々です。当社はビジネスモデルとして『BtoBtoX』を掲げていますし、われわれのテクノロジーが表舞台で活躍する方々の力になれればいい。その上で、一緒に社会課題を解決できるような仕事をしていけたらうれしい」。取材終了後、プロジェクトチームの謙虚な笑顔が、強く印象に残っています。
「生産者の方々の喜びの声はもちろんですが、コンソーシアムに参加し、スマート農業を推進する立場にある事業会社の方たちから感謝されたことも大きかった」と語る鈴木与一。メーカーの枠を越えてさまざまなデータを一元管理できるThings Cloud®の名前を覚えた事業会社も多かったに違いありません。
「ドコモビジネスとしては、今回のような農業の実証実験に参加するのは初めてのことでした。この機会を通じて農業はもちろん、水産業といった日本の自給率を支えるプロジェクトに携わっていけたらと考えています」と笑顔を見せる鈴木与一だが、自分たちはあくまでも舞台裏から支えるのが仕事だと言います。
「今回のプロジェクトの主役は、コンソーシアムの方々です。当社はビジネスモデルとして『BtoBtoX』を掲げていますし、われわれのテクノロジーが表舞台で活躍する方々の力になれればいい。その上で、一緒に社会課題を解決できるような仕事をしていけたらうれしい」。取材終了後、プロジェクトチームの謙虚な笑顔が、強く印象に残っています。
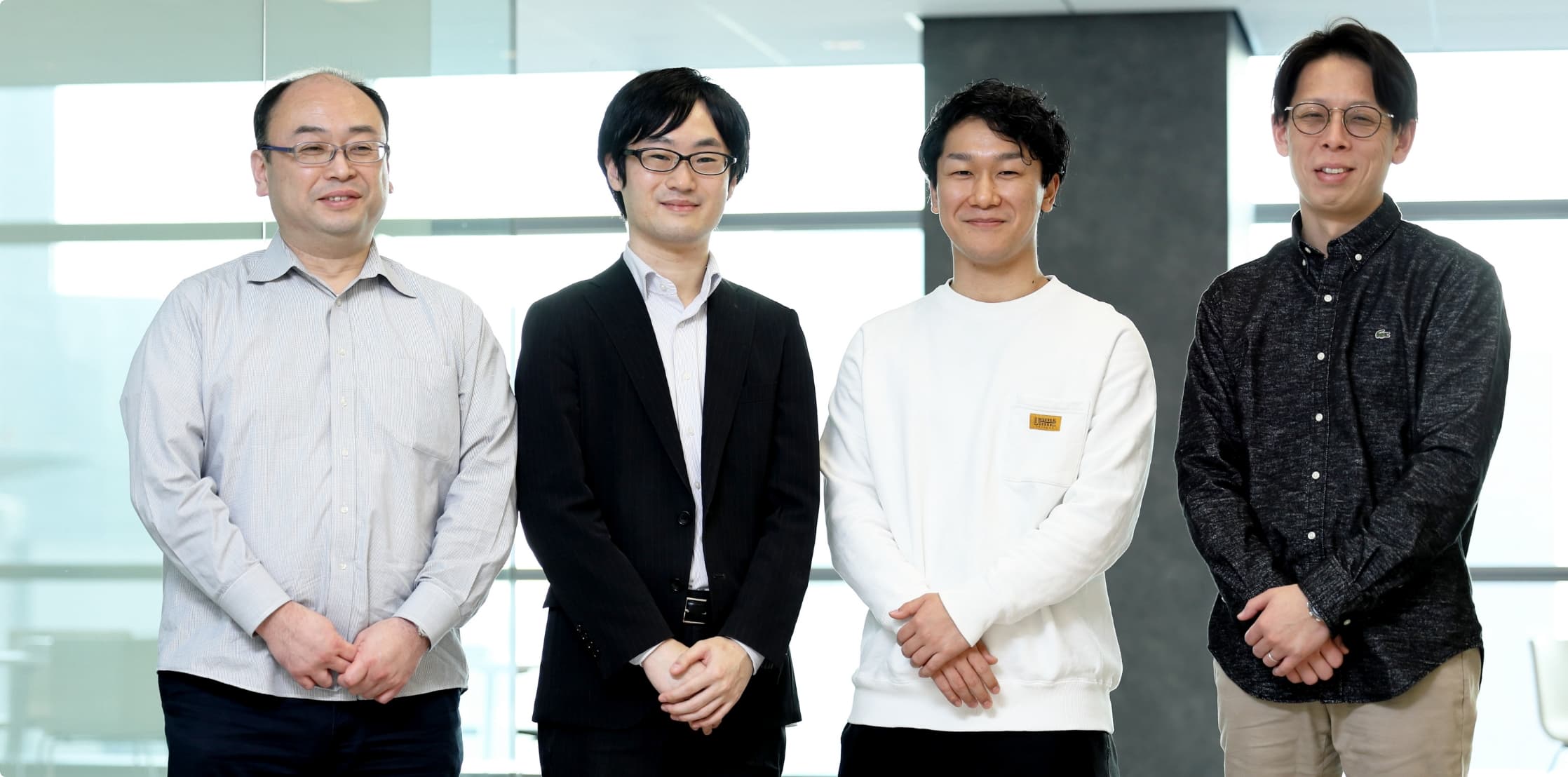
※掲載内容は2021年11月時点のものになります
※十分な感染対策を行い、撮影時のみマスクを外しています
※十分な感染対策を行い、撮影時のみマスクを外しています