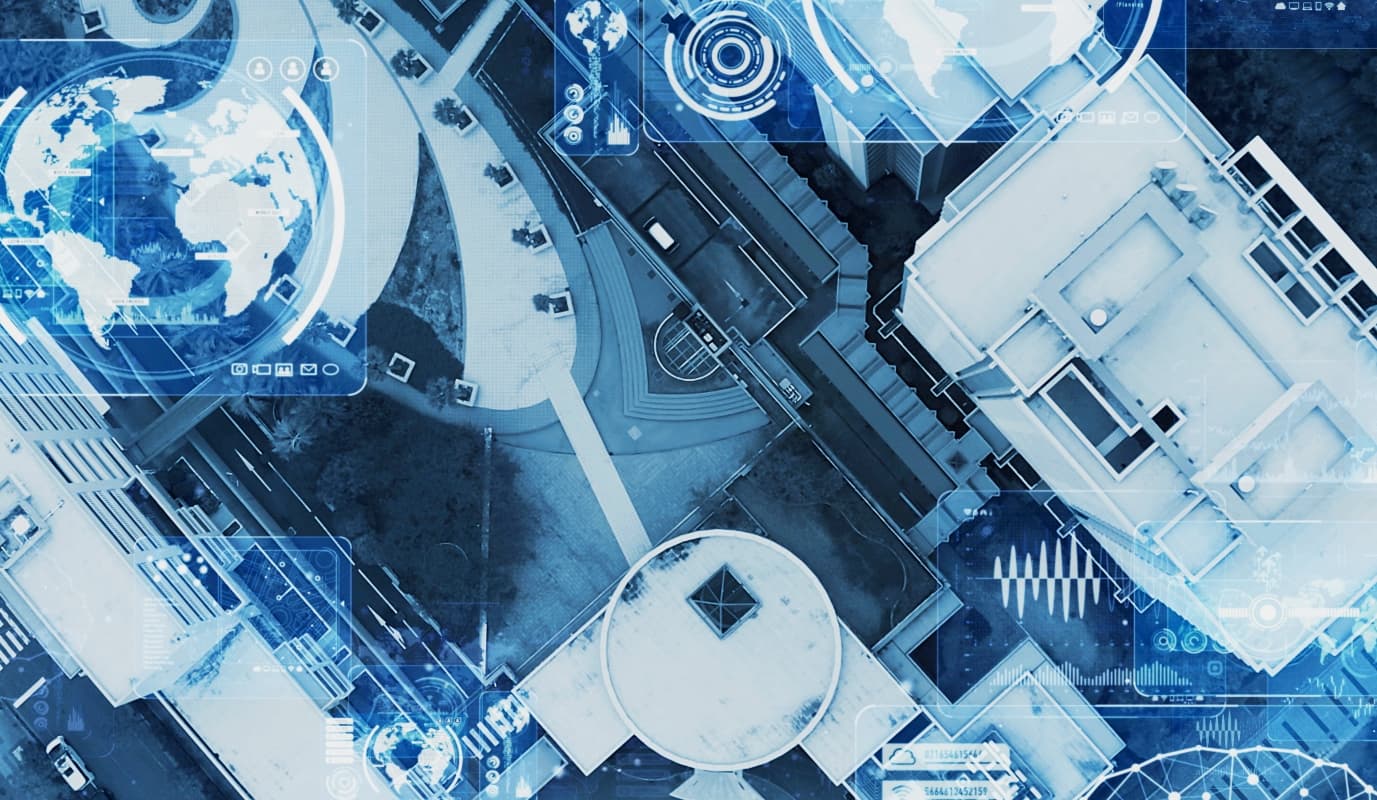ドコモのプロジェクト事例

超高速・大容量ネットワーク
世界初の次世代ネットワークを構築
OUTLINE
めざしたのは、将来の高速・大容量通信を支えるインフラ基盤となる次世代ネットワークの構築。中継装置を半減させることで、中長期で見れば約100億円のコストダウンも見込まれます。
光伝送装置の開発にはじまり、光ファイバーケーブルの調達、そして670kmにおよぶ敷設工事。商用世界初のバトンをつないだプロジェクトチームが、東京から大阪にたどりつくまでの壮大な物語を振り返ります。
PROJECT MEMBER

インフラデザイン部

インフラデザイン部
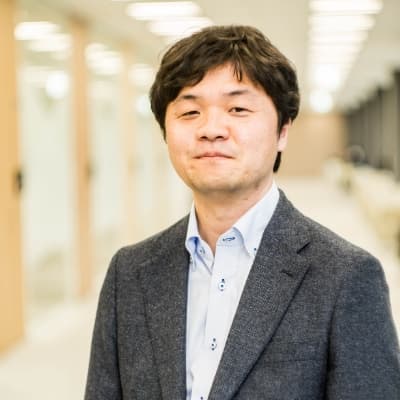
インフラデザイン部

インフラデザイン部

インフラデザイン部

インフラデザイン部

ソリューションサービス部
ICTイノベーション部門
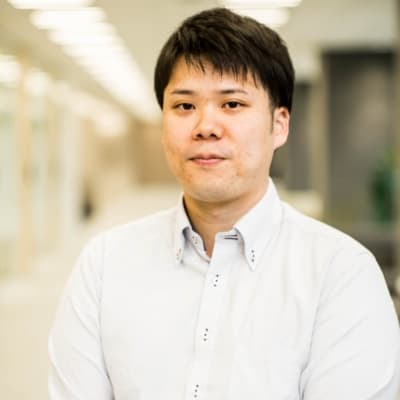
インフラネットワーク部
設計・構築ユニット
ROAD MAP
-
Phase 01 先行研究
NTT研究所において取り組んでいる、未来を見据えた新たな伝送技術の開発。その中で進められたチップの開発が、次世代ネットワーク実現の核となる。
-
Phase 02 計画立案
次世代ネットワークの構築に向け、問われたのは「性能」「信頼性」「経済性」。社会を支え続けるための新たな技術や工事の手法が求められた。
-
Phase 03 技術開発
高速・大容量通信を支えるインフラ基盤の実現に向け、世界最高水準の光ファイバーケーブル、伝送装置の開発に挑む。
-
Phase 04 設計
東京から大阪間、約670㎞に光ファイバーケーブルをどのようなルートで敷設するか。レジリエンスを高めながら、最短距離でつなぐルートを設計。
-
Phase 05 構築
光ファイバーケーブルを敷設、NTTビルへの伝送装置の設置。不具合が起きた際を見据え、外部パートナーとの保守・運用プロセスを構築。
-
Phase 06 導入
1日でも早く利用したいというお客さまの事業上の要請にチーム一丸となって応え、商用世界初となる長距離400Gbps伝送基盤の構築を完遂。次世代ネットワークサービスの提供を開始。
未来を見据え400Gbpsのエンジンを開発
探求心なのか、使命感なのか。河原は人知れずプロトタイプ(※)の開発、チューニングに心血を注ぎました。そんなある日、一本の電話が入ります。その声は、世界に先駆けて『最高水準のバックボーンネットワークにチャレンジしたい』というものでした。このプロジェクトが成功すれば、商用化としては世界初の事例です。
※ プロトタイプ…完成品ではなく、検証のために簡易的な試作機を作ること。

30年を支える世界最高水準のネットワーク基盤を
光ファイバーの調達を担当した佐野は「30年前の東京から大阪間のネットワーク基盤の構築には、4年の歳月を掛けました。しかし、今回の猶予は1年半。技術や工法が進化しているとは言え、これは非常に困難な仕事になるなと思いました」と当時を振り返ります。比較すると、4分の1の期間で世界最先端の技術開発からフィールドへ実装、ネットワーク基盤としてサービスを開始しなければならないのです。
「この実現には社内外の多岐に渡る関係者全員とビジョンを共有し、トラブルが発生した際は役割を越えて助け合う姿勢、そして協力会社との連携による新たな工法への挑戦が必要不可欠でした」と内山は舞台裏を明かします。

光ファイバーの調達と伝送装置の開発

東京と大阪をつなぐ670kmへの挑戦
「ハザードリスクのあるエリアは実際に自分の目で安全性を確認する、ケーブルを通す地下設備も深部側を選定していきました」。
酒井によれば、わずか数メートルの差がケーブルを災害から守り、信頼性を大きく左右すると言います。目には見えにくい地域特性によるトラブルポイントをパートナーと共有し、事故ゼロ、クレームゼロをめざしました。そして、30年に渡り維持できる性能に挑戦したのが、ケーブルの敷設を担当した小形です。従来の工法では2km毎にケーブルをつなぎ合わせるのが一般的でしたが、小形は従来の倍となる4km敷設にこだわりました。その理由は、接続損失にあります。ケーブルの接続点が増えることで、光ファイバーが情報を伝送する力は減衰していくのです。
「将来に渡り、光ファイバーの性能を維持するには4km敷設が必要不可欠でした」と語る小形は、新たな工法への挑戦を決意。パートナーと試行錯誤しながら670kmにもおよぶケーブル敷設工事を完走しました。
「なにもかもが手探りだったため、現場の方にはかなりの苦労をかけました。しかし、私が『ここは2kmにしましょう』と断念しかけたとき、逆に『最後までやり切ろうや』と背中を押してくれたのです」。

サービス開始後の保守・運用も視野に
「私の仕事は、開発チームが考案したものを仕上げるだけではありません。どんなに高性能な装置であっても、いつかは不具合を起こします。どうすれば保守・運用をスムーズにできるのかも考える必要がありました」。
そんな齊藤の言葉を、検証を担当した佐久間が引き継ぎます。
「今回の伝送装置には、最先端のテクノロジーが詰まっていました。だからこそ、これまでにないトラブルが起こるリスクがありました。まったく新しい伝送装置に対して何が起こっても即時対応できるように運用方法を新たに検討し、短期間でまとめる必要がありました」。
二人は開発段階から保守・運用を担うパートナーに声を掛け、実際の装置に触れてもらいながらフィードバックをもらいました。「この状態では故障復旧に時間がかかってしまう」と言われれば装置を改良し、「この問題は専用の工具があれば対応できるのではないか」と提案されれば工具を用意しました。
「ドコモビジネスでは普段からワーキンググループをつくって、計画段階からパートナーと連携しながら進めています。その一体感が、このプロジェクトにも漂っていた」と語る齊藤の言葉に、佐久間も頷きます。二人はサービス開始後の未来を睨みながら、パートナーとともにありとあらゆる懸念点を埋めていきました。
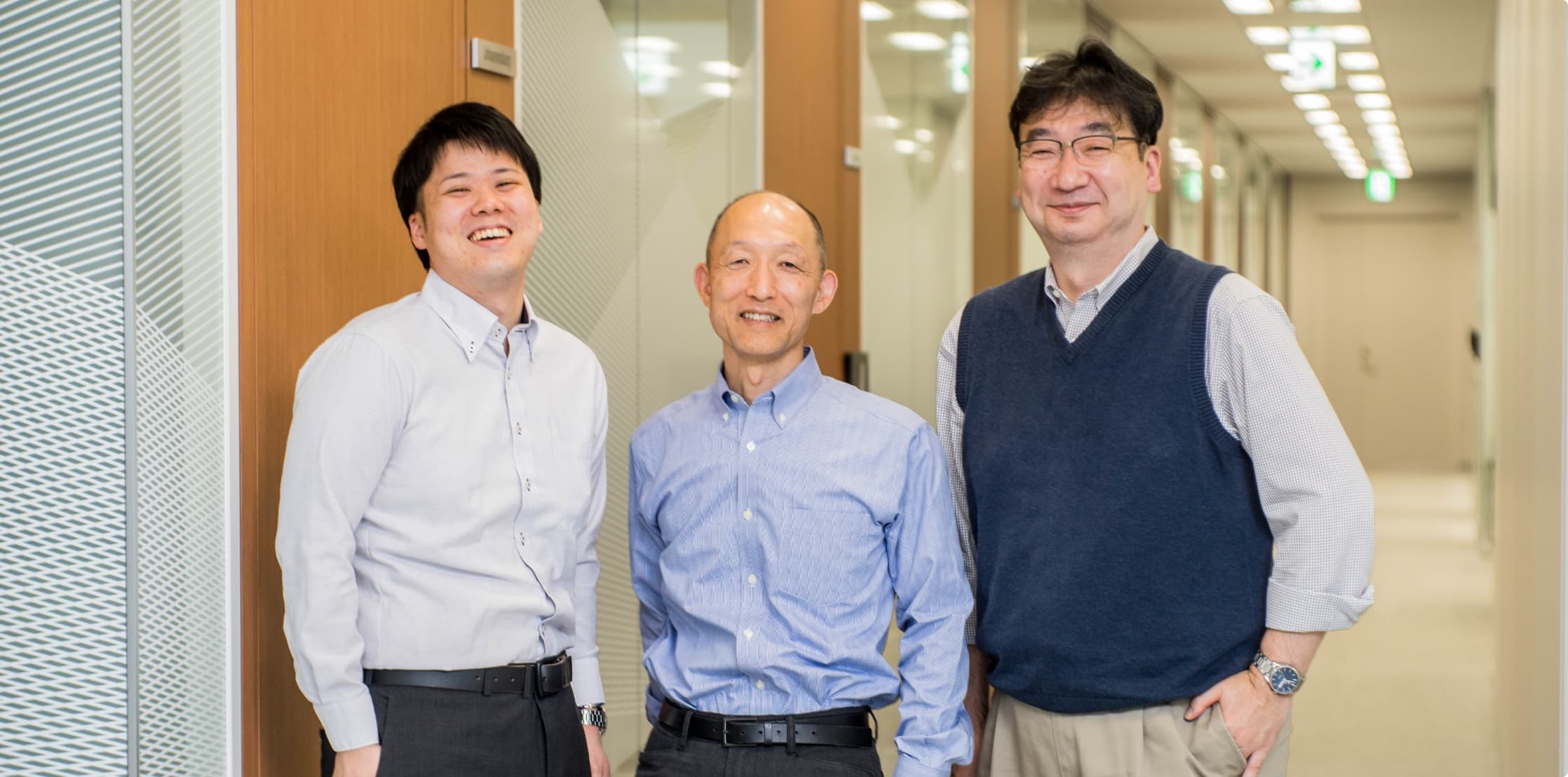
人、組織がつながり社会基盤へ
「納期を守るために、削減可能な工程は徹底的に減らしましたが、無理だけは絶対にさせることはしませんでした。たった一つの事故ですべての作業を停止しなければならない可能性もありますし、なによりも現地で工事に携わる大切な仲間の命にも関わることもありますから」。
そして、サービス導入の日、次世代ネットワークが670kmの隔たりを経てつながる瞬間を目の当たりにします。「事故ゼロ、クレームゼロで、ここまでたどり着くことができた。関係者全員への感謝の気持ちしかありませんでした」。
東海道ルートを構築後、「感謝の集い」を開催。現地で構築に携わってくれたパートナー会社(全11社、約200名)を招き、プロジェクトにおける苦労などを分かち合いました。「『世界初のネットワークに携われたことを誇りに思う』と仰ってくださる方もたくさんいたのです。決して簡単なことではなかったと思いますが、このプロジェクトに携わってくれたメンバーの誰1人欠けても、このネットワーク基盤の完成は無かったと思います」。
その後、ドコモビジネスとパートナーを含めたチームは、東海道ルートに続き中央道ルートを構築。国際ネットワークとの接続も果たし、今なお日本全国に次世代ネットワークをつなげるために奔走しています。
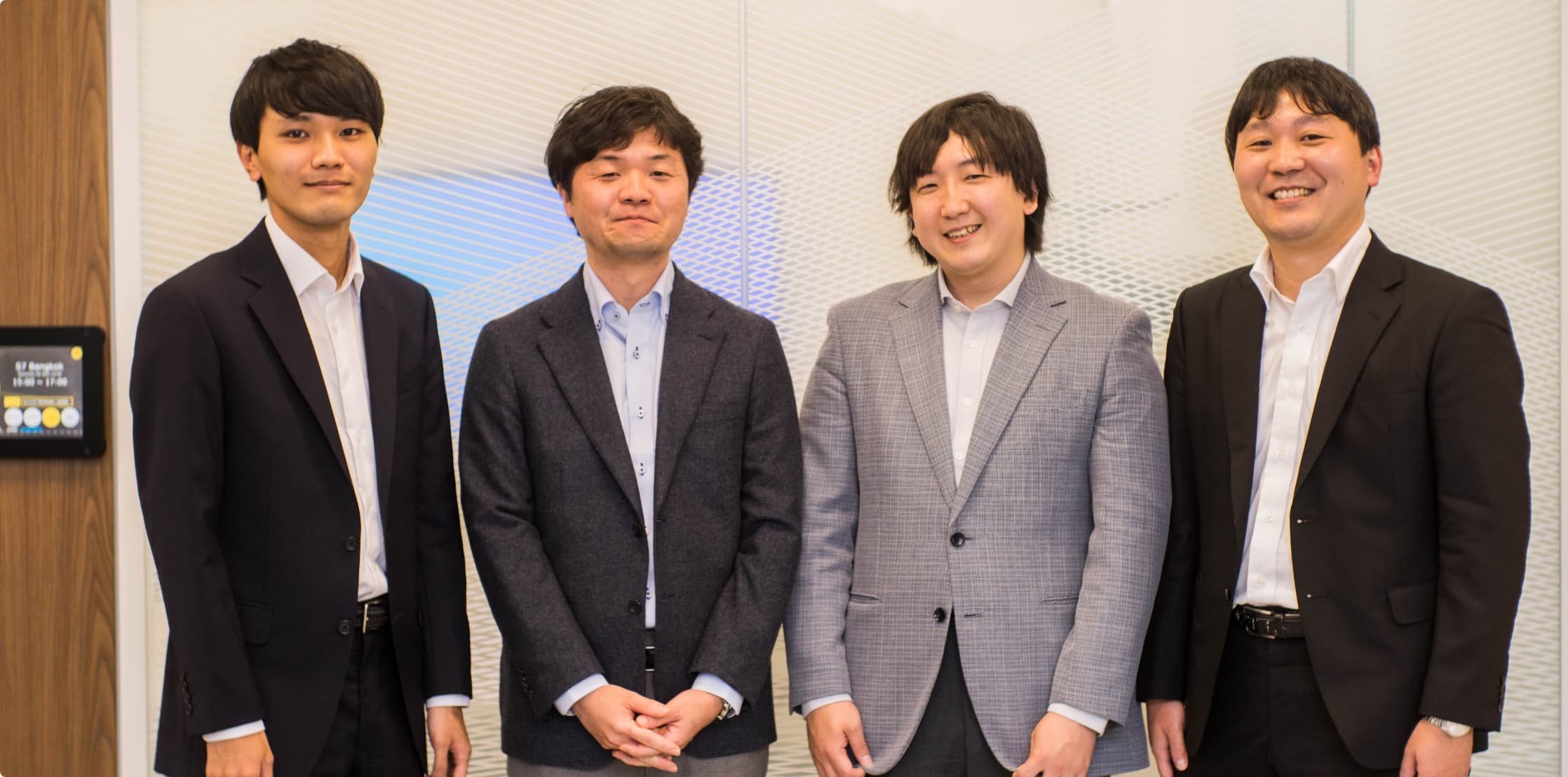
※十分な感染対策を行い、撮影時のみマスクを外しています